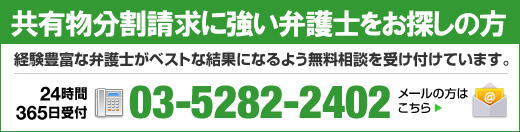共有物分割のための不動産競売
申立が必要
共有物分割訴訟を起こして、和解が成立せずに競売を命じる判決が出ても、それだけでは競売手続は始まりません。競売手続を行うためにはあらためて競売申立をする必要があります。
なお、競売になると値段が大幅に安くなるかについてはこちらをご覧ください。
また、他の共有者の持分が競売にかけられて心配されている方はこちらをご覧ください。
共有物分割のための競売に必要な書類
これは東京地方裁判所に競売を申立をした場合の必要書類です。他の裁判所ではこれとは若干異なることがあります。
・競売申立書
・発行後1ヶ月以内の不動産登記事項証明書
・公課証明書
・固定資産評価証明書(登録免許税計算のために必要となります)
・(当事者の中に法人がいる場合)商業登記事項証明書
・共有持分権利者全員の住民票
・(代理人に申立を依頼する場合)委任状
・競売を命じる判決正本
・公図写し
・建物図面
・住宅地図などの物件案内図
・不動産競売の進行に関する照会書
共有物分割のための競売の費用
これも東京地方裁判所に申立をした場合の費用です。
1.印紙代
競売を命じる判決正本1通につき4000円。
2、予納金
主として不動産の現況調査を行う執行官の費用や共有不動産の評価を行う評価人(不動産鑑定士)の費用に充てられます
物件の固定資産税評価額が2000万円未満 60万円
物件の固定資産税評価額が2000万円以上5000万円未満 100万円
物件の固定資産税評価額が5000万円以上1億円未満 150万円
物件の固定資産税評価額が1億円以上 200万円
3,登録免許税
競売手続は差押登記をすることによって始まりますが、この差押登記に登録免許税という費用が必要です。この金額は、物件の固定資産税評価額の1000分の4となっています。
4,郵便切手 92円切手1枚
共有物分割のための競売の手続の流れ
競売申立は他の担保権実行の競売や強制競売と異なる点はありますが、競売手続が始まってから配当手続に入る前までの手続の流れは他の競売手続と異なることはありません。ここでは順調に手続が進んだ場合の大まかな手続の流れを説明します。
1,現況調査報告書作成
まず執行官が不動産の現況調査を行って、現況調査報告書を作成します。
2,評価書作成、売却基準額の決定
評価人(不動産鑑定士)が不動産の評価書を作成し、裁判所が評価書に基づいて売却基準額を決定します。この売却基準額は市場価格の7割程度と言われています。
3,物件明細書の作成
裁判所が競売にかかった不動産の売却条件を確定した上で物件明細書を作成します。
4,入札期間、開札期日、売却決定期日の決定
5,最高価買受人に対する売却許可決定
6,代金納付
買受人が代金納付をした時点で競売不動産の所有権が買受人に移転します
共有物分割のための競売の配当手続
売却代金を持分割合に応じて割り付けます。
次に割付額から共益費用、抵当権などの優先担保権者、交付要求債権者、配当要求をした一般債権者に対する配当を行います。
その後に残った金員を共有者に売得金として交付します。
共有不動産に担保権が設定されている場合
共有不動産に担保権が設定されている状態で共有物分割のための競売手続を進めた場合に、担保権を消滅させて競売手続を進めるか、担保権付き不動産として競売手続を進めるかについて実務上争いがありました。しかしこの点は最高裁平成24年2月7日の決定により、担保権を消滅させて競売手続を進めるものとされました。
このように、担保権を消滅させて競売手続を進めることにすると、担保権者にとって安い金額で競売手続を強制されると不都合ということにもなるので、競売によって共有者が代金を得られる見込みがないと判断されたら競売手続は原則として取り消されることになります。これを無剰余取消といいます。
この無剰余取消がされるか否かの判断は、買受可能価額で優先弁済されるべき債務と手続費用をまかなうことができるかによりますが、買受可能価額というのは前述した売却基準額の8割とされています。売却基準額は前述したとおり市場価格の7割程度とされていますから、買受可能価額は市場価格の56パーセント程度となります。市場価格の56パーセント程度で手続費用と優先弁済されるべき債務の支払ができなければ原則として競売手続が取り消される訳ですから結構厳しいハードルになります。
共有不動産の売却・共有物分割請求に強い福本法律事務所は、破産管財人、成年後見人として数多くの不動産売買を行った経験を生かして、単純に分割の交渉をまとめるだけではなく、実際の不動産売買のサポートを行い、売買代金が決済されるまでをフォローいたします。
無料相談を行っていますので、お気軽にお電話ください。