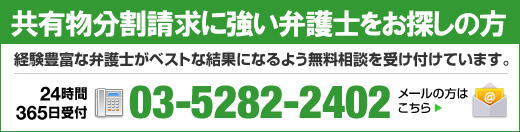共有物分割請求手続
共有物分割請求をするには、最初に共有物分割協議をする必要があります。
相談者の中にはさんざん話し合いをしてもらちがあかなかったから、すぐに訴訟、競売をして欲しいという方もおられます。
ですが、法律では「共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求できる」と規定されています。訴訟提起の要件として「共有者間に協議が調わない」というのがあるために共有物分割協議をせずに訴訟提起をすると、訴訟提起の要件がないから共有物分割訴訟は認められないなどと相手方から言われるおそれがあります。
このように、訴訟提起の要件を備えるためにも、最初に共有物分割協議をする必要があります。
1,共有物分割協議
法律では共有物分割協議の方法についての規定はありません。
実際に会って話し合いをする方法でも電話でやりとりをする方法でも手紙や電子メールでやりとりをする方法でもかまいません。
ですが、訴訟になったときに、相手方から「共有者間に協議が調わない」という要件を備えてないから共有物分割訴訟ができないなどと言いがかりをつけられないためにも、最初に配達証明付きの内容証明郵便で共有物分割協議の申入をすべきです。これは共有者全員に送付する必要があります。
そのような方法をとれば、共有物分割協議の申入をしたことについて証拠で証明することができますので一定期間経過しても共有物分割協議が成立していなければ、「共有者間に協議が調わない」の要件を備えたと証明することができ、相手方から無用の反論を受けずにすみます。
かたくなに適正価格での持分売買や共有不動産共同売却を拒絶していた人でも共有物分割請求に強い弁護士が代理人として共有物分割協議の申し入れをしただけで、持分売買や共有不動産共同売却に応じてもらえることも少なくありません。
共有物分割協議の申入をして、相手から何の応答もなかった場合、話し合いをしたが話し合いがまとまらなかった場合は「共有者間に協議が調わない」ことになるので共有物分割訴訟を起こすことができます。
2,共有物分割訴訟
共有物分割協議が調わなければ、共有物分割訴訟を提起することができます。
共有者全員と当事者にする必要があります。
裁判所は被告となる相手方のいずれかの住所地又は不動産所在地を管轄する地方裁判所に提起することになります。不動産を対象とする訴訟ですので簡易裁判所に訴訟提起することはできません。
請求の趣旨で求める判決の内容を記載します。競売を命じる判決を求めるのか、代償分割の判決を求めるのか、現物分割を求めるのかのいずれかです。
通常の訴訟ですと原告が求めた請求の当否を判断すればよいのですが、共有物分割訴訟の場合は共有物の分け方を決める裁判ですので、そもそも共有物分割請求権がない場合や共有物分割請求権があってもこれを行使するのが権利濫用にあたる場合以外は、何らかの方法で裁判所は共有物分割の方法を決めざるを得ません。ですので当事者が請求したのとは異なる内容の分割方法を命じる判決を出すこともできます。
共有物分割請求に強い弁護士が共有物分割訴訟を提起した場合、判決になると競売を命じる判決が出される事案では競売を命じる判決が出される旨を主張していますので、相手方に状況を理解してもらうことによって、訴訟提起をした場合でも判決になるとは限らず、むしろ和解で決着することが多いです。
共有物分割訴訟についての詳細は共有物分割訴訟のページもご覧ください。
3,共有物分割のための競売
共有物分割協議をしても、共有物分割訴訟を提起しても、共有不動産の分け方が決まらない場合に競売を命じる判決が出されることがあります。
競売を命じる判決がだされた場合に、この判決正本を添付した上で競売申立をすることができます。これは共有不動産全体に対する競売になります。このように共有不動産の処分に反対している持分権利者がいても競売を命じる判決に基づいて競売手続を行えば、共有持分権を失うことになります。
競売手続については共有物分割のための不動産競売のページもご覧ください。
共有物分割請求の関連ページ