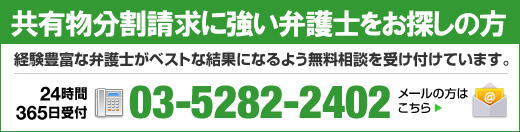遺産共有とは
死亡していた人が有していた財産について、亡くなった人の法定相続人が2人以上の複数である場合、遺産分割がなされるまでの間、相続人の相続分に従って法定相続人に共同で帰属していることになります。この遺産分割までの間に法定相続人に法定相続分に従って共同で財産が帰属している状態を遺産共有といいます。
遺産共有と共有物分割請求
この遺産共有の状態の時に、法定相続人は法定相続分に従った相続登記をすることができます。この遺産共有状態で法定相続分にしたがった相続登記をする場合、法定相続人のうちの1人のみでも相続登記申請をすることができます。ただし登記申請をしなかった法定相続人には登記識別情報(権利証)が交付されませんので、不動産を処分ないし担保設定する際に、登記識別情報がないために司法書士などによる本人確認が必要となり、余分な費用がかかるという不利益が生じることになります。
いずれにしても、法定相続人が法定相続分に従った相続登記をした場合、登記簿だけを見ると、不動産が共有状態になっているために、共有物分割請求ができそうに見えます。
しかし、遺産分割を行わずに法定相続人が法定相続分に従った相続登記手続によって共有登記がされている場合には、共有物分割請求をすることはできないと解釈されています。この解釈は最高裁の昭和62年9月4日の判例でも示されています。最高裁判例が共有物分割請求を否定している理由は、遺産分割を行うべきということにあります。
遺産共有状態でも共有物分割請求ができる場合
遺産分割をしないで法定相続分に従った相続登記をした場合に共有物分割請求をすることはできないと書きましたが、このような場合でも共有物分割請求をする方法はあります。
それは、法定相続分に従った相続登記をした後で、法定相続人の人が相続登記で取得した持分を法定相続人以外の第三者に譲渡する方法です。この持分を譲り受けた第三者は法定相続人ではありませんので、共有状態を解消する方法は遺産分割ではなく、共有物分割請求となります。このように法定相続分を法定相続人以外の第三者に譲渡すれば、第三者は共有物分割請求をすることができます。この解釈は最高裁昭和53年7月13日の判例で示されています。
私もこれまで取り扱った案件の中に、遺産分割によって共有登記がされている部分と遺産分割が行われていない部分があるものがありましたが、遺産分割が行われていない部分について法定相続人以外の第三者(依頼者の子供)に持分譲渡するという方法で、遺産分割を行わずに全て共有物分割請求で解決を図ったことがあります。
遺産共有状態での遺産分割
上記のように法定相続人以外の第三者に法定相続分を譲渡すれば共有物分割請求をすることができますし、このホームページのトップページにも書いたような遺産を共有で取得するという内容の遺産分割協議書を作成した上で共有登記をした場合にも共有物分割請求をすることができます。
しかし、第三者への法定相続分の譲渡をすることができず、遺産を共有で取得するという内容の遺産分割協議書の作成をすることができない場合は、遺産分割によって遺産共有状態を解消する他ないことになります。
遺産共有状態で共有物分割請求を考えておられる方は、共有物分割請求の手続をとれば持分を適正な現金に替えるのが比較的容易なのに、遺産分割の手続をとると、時間がかかってしまい、現金にするのが容易でないといった遺産分割手続に対して不満をお持ちなのではないかと思います。
しかし遺産分割手続をとった場合であっても、このホームページに書かせていただいた考え方(持分を適正な金額に替えることを求め、応じられなければ競売も辞さない旨を主張する)を主張すれば、共有物分割請求をしたのと同じように、不動産の共同売却か、持分を適正な金額で買い取ってもらうかのいずれかで早期に解決することも充分に可能です。このように遺産分割手続をとる他ない案件でも法定相続分を適正な現金に替えることは充分可能ですので、当事務所までご相談ください。