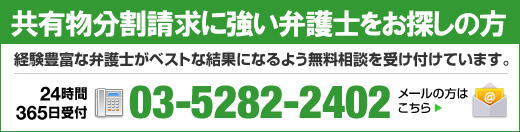現物分割
分割方法は遺産分割協議又は、訴訟提起後も和解が成立した場合は当事者の意向によって決まります。
訴訟提起をしても和解が成立しない場合に裁判所が分割方法を決めることになります。
裁判所が分割方法を決める場合、法律上、現物分割をするのが原則となっています。
ただし「共有物の現物を分割することができないとき」「分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき」は競売を命じることができると規定されています。
そこでどのような場合に現物分割が命じられて、どのような場合に現物分割が命じられないかを具体的に見ていきます。
共有物分割請求の対象が区分建物1棟(分譲マンションなど)の場合、物理的に建物を2つ以上に分けることはできません。
また建物1棟の場合、区分所有にすることができる建物であれば区分所有にするという方法で現物分割することも可能ですが区分所有にするためには建物図面が必要になり建物図面を入手できなければ物理的に建物を2つ以上に分ける方法がないことになります。
従ってこれらの場合は「共有物の現物を分割することができないとき」にあたり現物分割を命じられることはありません。
共有物分割請求の対象が土地一筆で建物の敷地になっている場合も現物分割をすることができないと考えられます。
共有物分割請求の対象が建物の敷地になっていない更地の場合は、分筆というて続きによって2つ以上の土地に物理的に分割することは可能です。
ですが物理的に可能であるからといっても分筆すると土地の利用が難しくなるなどの場合は「分割によってその価格を著しく減少させるおそれがある」として現物分割が命じられないものと考えられます。
このように見てくると、現物分割が原則ではありますが、現物分割が命じられる事例は多くないということがお分かりいただけると思います。
共有物分割請求の関連ページ